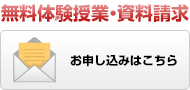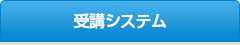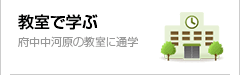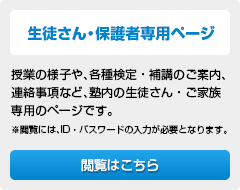月別 アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (2)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (2)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」
英進アカデミー「勝利のブログ」
第二段階
来週からは、本格的に入試準備を進めていく。
私立単願受験生や、都立(公立)高校の受験コース
によっても試験科目が5科目か英数国の3教科受験
に分かれる。
英検や、漢検等を取ったみんな「よくやった!」
少しでも受験に有利になるよう、また学力アップの
ために頑張ってきたみんなの勝利だ。
さあ受験勉強の第二段階だ。集中して取り組もう。
(by 英 一)
(英進アカデミー)
2013年11月23日 18:04
| コメント(0)





燃え尽きた?
学校によってはまだ試験はあるけれど、一通りの対策
も終わり。一足先に試験を終えた学校のみんなは、教科
によっては答案の返却も始まっている様子です。
予想以上に良い結果が出ていて安心です。
が、やはり今回の試験準備は皆にとって大変だったのか
少々バテ気味の様子。部活動も再開しているから尚更ですかね?
試験のすべての結果が出たら皆も安心でしょう。
休めるときにしっかり休んでおくことも大切な勉強ですよ。
(yamauchi)
(英進アカデミー)
2013年11月21日 17:40
| コメント(0)





試験終了後の注意点 補足(推薦試験、一般試験)
試験終了後の注意点は、入試においても同様の事が言えます。
入学試験後の過ごし方で「推薦入学」と「一般入学」それぞれの
生徒の、進学後の成績に大きく影響するからです。
一般的に「一般入学」の生徒の入学後の成績の伸びは
「推薦入学」の生徒のそれを上回るといわれています。
「推薦入学」は私立であれ都立(公立)であれ、「一般入試」
より1か月以上早く結果がでます。
仮に推薦で合格したとして入学までのおよそ2~3か月間、
おそらくは楽しい日々を送ることでしょう。勉強のない充実
した日々と、同級生より一足先に合格した喜びに包まれながら・・・
しかし前講座で示した通り、「入試後も勉強を継続した生徒」と
「そうしなかった生徒(推薦合格)」との学力差はすでに
広がっているので注意です。人間思ったより「忘却は速い」です。
高校入学直後に実施される「統一試験(中学内容)」ではっきりします。
目的達成後(入試)は「急激な忘却」と下手をすれば
「燃え尽き症候群」の可能性でてくるので注意が必要です。
いずれにしても「脳の整理運動」が重要であることは
覚えておきましょう。
(7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年11月20日 21:52
| コメント(0)





定期試験終了後の注意点 Ⅱ
目標達成後の「急激な忘却」は、裏を返せば「長期記憶」
に変換しやすい状態でもあります。
一つずつ、丁寧に復習する「精神的余裕」があるので
問題をじっくりとより深く理解することができます。
納得できた内容ならば、記憶は長期に留まりやすい。
まずは「いやでもやりましょう」10日前後の時間をかけて
「脳の緊張をといていきます。」勉強内容は、
「試験準備で使った教材」が良いでしょう。
仕上げに試験問題を解き直すことで、得点のみならず
内容の「定着」と「理解度」が格段に上がります。
何よりも入試に出題される重要事項が脳内に長期で
保存されます。いわゆる「脳の整理運動」です。
(7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年11月20日 21:40
| コメント(0)





定期試験終了後の注意点
定期試験が終わると当然「ホッ」としますね。
試験のために一生懸命に準備してきたわけですから
当然といえば当然の流れです。
しかしこの「ホッとする」は結構こわいものです。
①人は目的を達成した瞬間から急激に「忘却」を始める。
②特にいやいや続けてきた勉強=いやなこと=忘れたい
となります。
「ホッとする」のは当然のこととしても、し過ぎに注意です。
今回の試験は乗り越えられても、いずれ
「入試のためにまたやり直さなければならない!」ことになる。
現在中3生はじめ受験生ならなおのこと。
もう「やり直す時間はない」のですから・・・
(7C's教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年11月20日 21:27
| コメント(0)





試験準備
本日は数学、理科。目処が立ったところで提出課題。
夕飯までに終了しました。
受験生の中には、夕食を取らずに夜遅くまで頑張った
生徒もいました。やった分だけの成果があって、志望校
合格への可能性が広がることを望むばかりです。
しかしみんなよく頑張るね。さらに応援したくなります。
明日(日曜日)も午前10時からですよ。
(yamauchi)
(英進アカデミー)
2013年11月16日 21:20
| コメント(0)





スパルタか理論派か? Ⅲ
要望に応えるのが塾講師のしごとである。
何事にも「期限」というものがある。期限内に目標を達成
することは当然のことであり、時間は待ってはくれない。
目標を達成するのには「スパルタ指導」が最適である。
その結果成績が上がり志望校合格を手にした生徒たちは喜んでいる
はずである。何よりも「志望校合格」を目標に入塾したのだから。
客観的な意見を述べておくと、学習塾には「厳しい講師」と「そうではない講師」
が混在している(個人塾は塾長が全てだが)。講師それぞれのキャラクター
があって、それらが良いバランスを保つことで教室は成り立っているともいえる。
確かに、「わたしは〇〇先生は好きだけど、□□先生は苦手」
ということもある。生徒の学力レベルにも差があるのだから
一概には「スパルタが良い」とは言えないのかもしれない。
(by 英 一)
(英進アカデミー)
2013年11月14日 14:13
| コメント(0)





スパルタか理論派か? Ⅱ
しかし結論からいえば「双方の生徒さんはそれぞれ力を付けていた!」
学習塾ではどうだろう?「7C's教育研究所(セブンシーズ)」でも検証され
ているので、ここでは個人の意見を述べるに留めておく。
学習塾には大抵「厳しい講師」と「そうでない講師」が存在する。
生徒の成績の上がり具合で比べることができそうである。
一定期間(例えば次回の定期試験まで)で比べると、圧倒的に「スパルタ
授業」が結果を残す。スパルタ志向の私には朗報だ。
ところが成績の評価範囲を学期、一年、と広げていくと意外な結果が。
スパルタ指導の成績は頭打ち、逆に「厳しくはないが、生徒の心をがっちり
掴み、十分なコミュニケーションをとっている講師(もちろん指導は的確)」
の指導では2次曲線的な学力向上がみられた。
単なる「スパルタ指導」では通用しないのだろうか?
(by 英 一)
(英進アカデミー)
2013年11月14日 13:46
| コメント(0)





スパルタか理論派か?
やっていた。「スパルタ」か「理論派」が勝つのか興味深く見入ってしまった。
詳細は忘れたが、同レベルに絵が下手な二人にそれぞれの講師が担当し
、期限内でどれだけ上達するか?という内容だった。番組ではどちらの
講師が「スパルタ」でどちらが「理論派」かはよくわからなかったが・・・
「スパルタ」も「理論派」も、到達するまでの「アプローチ」は異なるものの、
要所要所では指導に共通する部分がある事が興味深かった。
これ、勉強の世界でも議論のわかれるところ(どの世界も基本は同じだが)
折角なので、本件を学習塾についてもう少し掘り下げてみることにする。
(by 英 一)
(英進アカデミー)
2013年11月14日 13:32
| コメント(0)





「もうひとひねり」が身に付くと・・・Ⅲ
改めて「もうひとひねりの勉強」について考えます。今後の勉強が
お子様にとって一番大切な「自学自習」を身に付けるための方法です。
①「機械的な作業」をやめる。
*勉強後?に必ずできるようになったか「確認テスト」を実施する。
②比較的基本的な問題を中心に。「解答スピードを徐々に上げていく」
*取りかかりは「質(内容理解)」を重視。慣れたら「問題量」重視
*同時に毎回正答率(100%目標。100%を維持しつつ時間短縮)
単純な作業ですが、この①②を日々の勉強に加えるだけで
「集中力」や「持続力」、「得点力」がアップします。しかも、前々回の
冒頭で述べた「凡ミス」が激減します(凡ミスが減るだけですでに得点アップです)
単純すぎる内容なので「継続が難しい」かもしれません。「自立学習」が
未だ確立していないお子様ならば尚更です。しばらくの間はご家族の
見守り(一緒にやる)が必要かもしれません。
また学習塾や家庭教師に依頼する場合でも、単に教えるだけでなく
お子様の学習状況を十分に把握し考慮して「もうひとひねり」を正しく、
しっかり指導できる教室(講師)か否かを確かめて選びましょう。
(by 7C’s教育研究所)
(英進アカデミー)
2013年11月10日 18:29
| コメント(0)





<<前のページへ|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|次のページへ>>