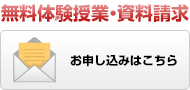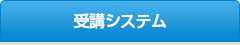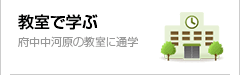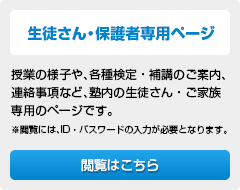月別 アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (2)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (2)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (3)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (8)
- 2020年5月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (20)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (20)
- 2019年11月 (18)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (19)
- 2019年7月 (14)
- 2019年6月 (25)
- 2019年5月 (39)
- 2019年4月 (25)
- 2019年3月 (28)
- 2019年2月 (37)
- 2019年1月 (35)
- 2018年12月 (37)
- 2018年11月 (28)
- 2018年10月 (27)
- 2018年9月 (23)
- 2018年8月 (21)
- 2018年7月 (23)
- 2018年6月 (25)
- 2018年5月 (24)
- 2018年4月 (14)
- 2018年3月 (10)
- 2017年8月 (34)
- 2017年7月 (19)
- 2017年6月 (48)
- 2017年5月 (49)
- 2017年4月 (36)
- 2017年3月 (41)
- 2017年2月 (52)
- 2017年1月 (54)
- 2016年12月 (52)
- 2016年11月 (55)
- 2016年10月 (52)
- 2016年9月 (48)
- 2016年8月 (50)
- 2016年7月 (43)
- 2016年6月 (49)
- 2016年5月 (47)
- 2016年4月 (34)
- 2016年3月 (31)
- 2016年2月 (38)
- 2016年1月 (40)
- 2015年12月 (31)
- 2015年11月 (38)
- 2015年10月 (10)
- 2015年9月 (30)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (22)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (12)
- 2015年2月 (19)
- 2015年1月 (24)
- 2014年12月 (18)
- 2014年11月 (20)
- 2014年10月 (70)
- 2014年9月 (65)
- 2014年8月 (84)
- 2014年7月 (20)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (8)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (9)
- 2014年1月 (3)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (38)
- 2013年10月 (23)
- 2013年9月 (22)
- 2013年8月 (40)
- 2013年7月 (20)
- 2013年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > 英進アカデミー「勝利のブログ」
英進アカデミー「勝利のブログ」
成績が上がらない・・・上がる訳無い!
しかしプライドが勉強の邪魔になることは大いに有り得る。
数学の計算、英語の文法や単語連語・・・
自信があるからそれらを『勉強する意味』がわからない。
計算の途中式を書くのは面倒、分かっているのだから暗算で十分だ・・・
単語は分かる、分かっている単語を書くなんて時間の無駄、見れば十分・・・
とにかく理由をつけて、書かずに終えようとする中学生が多い。
見て覚えればそれで十分だと思っている中学生が多い。
当然、定期試験や模試の得点など上がりようもない。
確かに『大人の感覚』からすれば学びにそういう側面があるのも分かる。
しかし『大人は膨大な時間をかけて最小限の努力で身につけるすべを体得している』
だから大人の感覚で子供に勉強方法を指導するのは間違いだ。
多くの子供にはまだ『絶対的な経験値が不足している!』からだ。 つまり
要領よく勉強することなどできないことを理解した上で指導する必要がある。
年齢とともに『読む書く聞く話す』の経験値が増える。それに伴って
要領よく学ぶことができるようになっていくのである。
『声に出して読みなさい』そして『書きなさい!』
学力を、使えるレベルにするために、『手抜きや甘えた発想は禁物』だ。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年3月27日 17:55
| コメント(0)





君の弱点!
数学、英語、国語
もう既にやり終えた生徒もいるはずだが・・・
その勢いでもう一度はじめからやり直すと、きっと一度目と同じ間違いをする。
二度目をやり終えたら、三度目を繰り返してみる。
解答時間が短くなって、◯の数も増えているはずだ。
同時に、初回から3回連続して間違えてしまった問題があるだろう。
その問題こそが『君の弱点!』
今まで以上の得点を取ろうと思ったら、その問題に集中するだけでいい。
次回の試験では『納得の得点』になるだろう。
しかし、誰しも出来る問題をやらない。時間の無駄であり、意味が無いと思うからだ。
多くの中学生がそう思う中、『自分だけはやってみる!』ことに意義がある。
そしてチャレンジしたものだけが知る『得点力の世界』がそこにある。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年3月27日 17:41
| コメント(0)





本日2016春期講習会初日
英進アカデミーでは新年度より、『より総合力を養成する授業』
に入力します。知識を広げ、理解を深める。思考力を高めるとともに
より高度な問題にも積極的に取り組むことが出来る学力を育みます。
定期試験での成果、模擬試験でも安定的な成果を残せるよう
指導いたします。この春期講習会では学習教科を数学、英語(国語)に絞り、
授業の流れや効率的な家庭学習の方法を身につけます。
同時に、6月の中間試験、英検漢検等の受験準備も始めます。
英進アカデミー 7C's教育研究所
(英進アカデミー)
2016年3月25日 14:51
| コメント(0)





受験まで1年・・・
内申点が数点違うだけで合否を分けてしまう。
必ずしもバランスの良い成績の生徒が有利というわけでもない。
お子様の学力状況から冷静に判断し、得意教科での『揺るぎない学力』
を早期に身につける必要がある。
あくまで、表は定期試験の結果と内申点からの推察である。
模試の偏差値による『入試当日の得点予想』は加味していない。
つまり、定期試験の得点が高いから模試の得点(偏差値)も高い、
とは一概には言えない。既学習範囲をすっかり忘れてしまっていれば
模試の結果(偏差値)は当然悪くなるはずだからだ。
受験勉強は『総合力』が必要。何度も繰り返し勉強することでしか
身にはつかない。よって時間もかかる。
受験まで一年を切った。この時期だからできることがある。
一日も早い本格的な受験勉強をスタートしてほしい。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年3月24日 17:25
| コメント(0)





自分と同じ学力レベルの友人が・・・
<表1>
A君の成績 数学 英語 国語 理科 社会 合計
100 50 80 100 70 400
B君の成績 80 80 80 80 80 400
<表2>
A君の通知票 数学 英語 国語 理科 社会 合計
5 3 4 5 3 20
B君の通知票 4 4 4 4 4 20
表1、2 よりA君B君ともに試験得点も通知票も同点である。
一概にどちらが良いとはいえないので、ともに次の試験でそれぞれ
各教科5点ずつ下がってしまったと仮定する。
<表3>
A君の成績 数学 英語 国語 理科 社会 合計
95 45 75 95 65 375
B君の成績 75 75 75 75 75 375
<表4>
A君の通知票 数学 英語 国語 理科 社会 合計
5 3 3 5 3 19
B君の通知票 3 3 3 3 3 15
表3、4より試験成績は同じだが、通知票に4点の差が生じてしまう。
通知票4点の差は換算点30~40点程度の差にもなる。仮にB君がA君と同じ高校へ
合格しようとするならば、その分B君は入試当日の得点でA君の得点を上回らなければならない・・・
①内申点を高く維持すること②得意教科が複数あることがみえてくる。
なんとも理不尽なことだが現実だ。日頃の勉強のひとつの指標にはなるだろう。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年3月23日 22:27
| コメント(0)





内申点と偏差値
自分の現在の学力を把握する必要がある。考慮するのは学校の
通知表(今週末に渡される)の成績と模擬試験における『偏差値』だ。
毎度のことだが入試は『内申点(通知表の点数)』と入試当日の得点の
総合得点で決まる。上位高校では双方の得点が高い方が断然有利だ。
現在、仮に内申点が高いとしても、偏差値(総合力)が高いとは限らない。
だから『公開模擬試験』や通っている塾の模試等を受験し、早期に自分の
『総合力(偏差値)』を知っておく必要がある。
注意点は、現時点での自分の学力であり、それが入試に対応できる
学力ではないということだ。内申点や偏差値は中学3年生時の学力如何で
上がりもするし、下がることだってある訳だ。
現在の高得点に安心し『油断する分だけ得点は下がる!』
その結果、行けるはずの志望校をみすみす逃がすことにもなり兼ねない。
新学期までに、中2,1生時の学力を付けておくこと。そのうえで中3生の
単元を消化していかなければならない。
一年後、志望校に合格するために、自分が今やるべきことが何かを考えよう。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年3月22日 16:44
| コメント(0)





スタートダッシュが・・・
しかし卒業生は毎年、1日でも早く受験準備に取りかかれば良かった・・・
と言います。入試は先手必勝です。
3学期が終わってホッとしているところでしょう。また、新年度に向け
気持ちを切り替える時期でもありますから、休めるうちに休んでおく
ことも重要な事です。受験が近づくにつれ体力勝負になりますからね。
毎日最低限の勉強を心がけて実践していくことも大切ですが、
『志望校の選択』だけは今のうちに決めておいたほうが良いでしょう。
併願校選びも大切な要素です。入試間近になって慌てて探す必要のない
ようにしておきましょう。家族や先輩たちの意見を聞きながら候補を絞るのもいいですね。
この時期の志望校の選定は今後の『勉強のモチベーション維持』に
大きく関わります。
『志望校の選択は今のうちに!』
『日々の最低限の勉強と併せて』 何事もスタートダッシュが肝心です。
7C's教育研究所 英進アカデミー
(英進アカデミー)
2016年3月19日 17:39
| コメント(0)





明確な記憶
得点を上げるために必要な事を挙げればきりがありませんが、もう1点。
『記憶を瞬時に思い出せること』です。
当然のことですが、試験には『時間制限』があります。
問題を見て、その解答法を瞬時に思い出せなければ
分かっているのにできない、つまり得点にはならないということです。
こんなに悔しいことはないでしょう。時間があれば解答できるのですから。
ということは、解答スピードも必要です。
解答スピードを上げるには、やはり『練習』しかありません。
分かったから大丈夫、解けるから大丈夫ということはないんです。
そのための家庭学習。だから最低限、その日のうちに覚えるべきこと
は覚え、『常に使えるレベルを維持』する必要があります。
『忘却』を乗り越えて『定着』させるのには相応の時間を要します。
それらの相乗効果が、以降の大きな学習効果につながります。
『心の準備』と『いま自分にできることに取り組むこと』
早速新年度を迎えるための準備を始めましょう。
7C's教育研究所
(英進アカデミー)
2016年3月17日 16:34
| コメント(0)





『忘却』とたたかおう!
そうでない生徒の違いは以下にあります。
問題が
①わかるようになる ②解けるようになる ③翌日、1週間後も解ける ④1ヶ月後も・・・ ⑤半年後も・・・
ところが、人間には『忘却』があります。上記①~⑤それぞれに『忘却』
が存在することも考慮する必要があります。実際には、
問題が
①分かるようになる・・・忘却 ②解けるようになる・・・忘却 ③翌日、1週間後も解ける・・・忘却・・・
段階が進むにつれて『忘却の度合い』は小さくなります。つまり『記憶に残っている』ということです。
常に高得点を取る生徒は①~⑤の段階を『忘却も踏まえ』クリアしています。
『記憶が正確』なので高得点を取れる、ということです。
一方、毎回の得点の状況から、多くの中学生は①②止まり
だということがわかります。折角問題が分かったのに得点できない。
解けるようになったのに得点できない。それは『忘却』のためです。
この忘却をどう解決するかが学力アップの糸口です。
『覚えていよう!』そう思いながら勉強に取り組んでみましょう。
自分でも気づかなかった自分なりの勉強法がきっと見つかりますよ。
7C's教育研究所
(英進アカデミー)
2016年3月17日 13:38
| コメント(0)





小学生時の基礎学習が中学での・・・
例年と少し異なる傾向が伺われた。
それは『漢字と計算』の弱さ。(中3時入塾生)
漢字の読み書き、計算のスピードと精度の悪さである。
学力偏差値の高い生徒でもその傾向がみられた。
偏差値の良し悪しに関わらず、常に高い生徒もいた。
漢字の読み書きや計算練習は、中学2年終了時までに小学生時より
8年以上も続けてきたはずの勉強の基礎だ。
如何に学力偏差値が高い生徒でも、基礎がなければ学力アップは望めない。
①漢字検定(3級以上。6月、10月実施)取得を目標に自宅学習を進める。
②国語の授業時における『記述』の比重を増やす。
③数学の授業において、解答スピードと精度を上げる。
④日々の家庭学習で①~③を必ず行う。
結果として偏差値の高い生徒たちは、この『漢字と計算』の
精度を上げる事で更に偏差値を上げることができた。
それ以外の生徒達にとっても入試時の大きな得点源となり得た。
中学で学力レベルを高く保つには、小学生からの『基礎学習』
は欠かせない。中学進級までに必ず身につけたい学習習慣だ。
(by 英 一 )
(英進アカデミー)
2016年3月16日 15:17
| コメント(0)





<<前のページへ|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|次のページへ>>